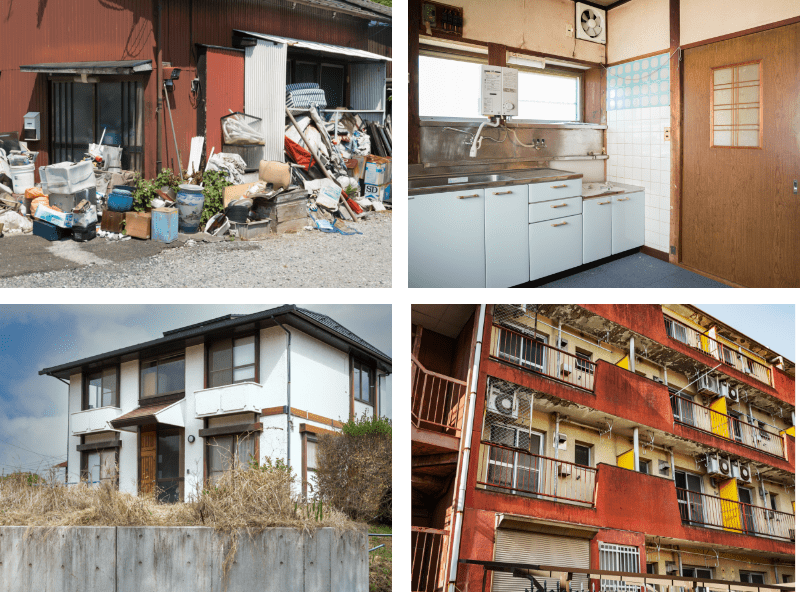根抵当権のある不動産の相続について!抹消する方法をご紹介

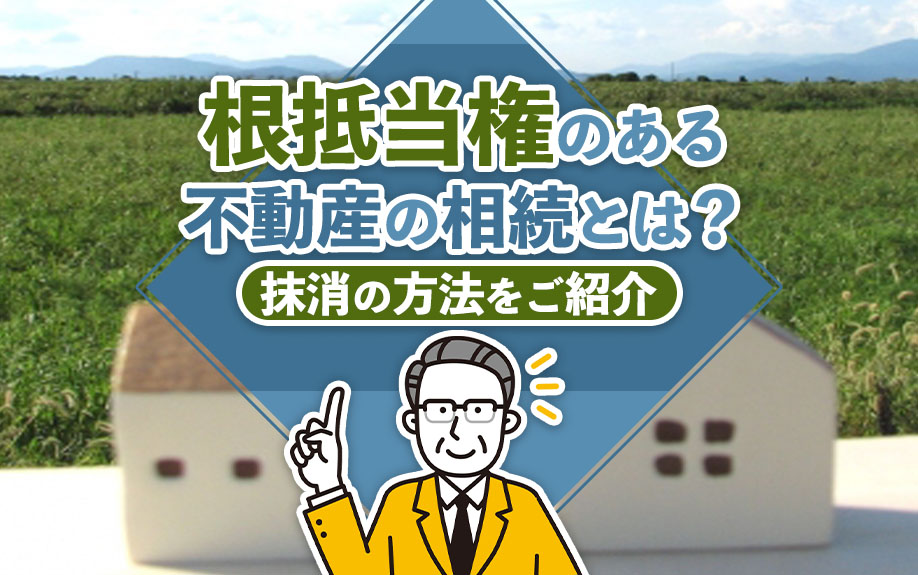
相続する不動産には、根抵当権と呼ばれる権利が設定されていることがあります。
それをそのまま相続する場合と抹消したい場合では、それぞれ異なる手続きが必要です。
そこで今回は、不動産の根抵当権とは何かにくわえて、根抵当権がある不動産をそのまま相続する方法と、根抵当権を抹消する方法についてもご紹介します。
不動産の根抵当権とは

根抵当権とは、設定されている限り該当の不動産を担保に何度でも融資を受けられる権利です。
極度額と呼ばれる融資の上限金額が決められており、この極度額に達するまでは何度でもお金を借りられます。
たとえば、極度額が5,000万円の根抵当権が設定されている不動産を担保に、毎回500万円ずつ融資を受けるのであれば10回の融資を利用することができます。
抵当権との違い
不動産に対して設定される権利のなかで一般的に知られているのは、抵当権と呼ばれる権利です。
抵当権とは、融資をおこなっている債権者が債務者の返済が滞ったときに不動産を担保として差し押さえられる権利です。
抵当権は、一度に借り入れられる金額が決められ、融資を受けられるのも一回限りですが、根抵当権は極度額の範囲内であれば回数や金額に制限はありません。
また、抵当権は債務の返済額や返済日が決められていますが、根抵当権には返済額や返済日の指定がないのが特徴です。
さらに、抵当権を設定した融資には連帯債務者を設定できますが、根抵当権を設定した融資には設定できません。
そして、根抵当権は、元本確定をおこなうと抵当権と同じ扱いになり、それ以上の借り入れができなくなります。
元本確定とは、借入額を確定させ、根抵当権を終了させるための手続きです。
なお、元本確定をおこなうためにはいくつかの条件がありますが、不動産の相続発生にも関わりがあります。
根抵当権がある不動産の相続を急いだほうが良い理由
相続人が複数いる場合は、話し合いの結果、全員が納得するまで不動産などの相続を確定させられません。
しかし、根抵当権が設定された不動産については、早めに相続人を決めて相続の手続きをおこなう必要があります。
根抵当権がある不動産の相続を急ぐべき理由は、相続開始から一定期間が過ぎても登記手続きが進んでいない場合だと、元本が確定してしまうためです。
また、相続が発生した不動産は、6か月以内に指定債務者の登記をおこなわなければ元本が確定します。
なお、根抵当権が設定されている不動産を相続放棄したい場合は、相続開始から3か月以内に手続きをおこなわなければなりません。
根抵当権がある不動産をそのまま相続する方法

故人の事業を承継するときなど、設定された根抵当権はそのままに不動産を相続したいケースもあるでしょう。
根抵当権をそのままにして相続したいときは、2つのパターンが存在します。
不動産の所有者と債務者が同じパターン
不動産の所有者と根抵当権の債務者が同じ故人であれば、根抵当権のある不動産をそのまま相続する手続きはスムーズに進むでしょう。
不動産の相続人は、不動産の所有者を変更する相続登記と、根抵当権が設定されている債務の名義を変更する指定債務者登記をおこないます。
これらの手続きにより、根抵当権の設定は維持されたまま、不動産の所有権と根抵当権の債務者としての役割を相続できます。
不動産の所有者と債務者が異なるパターン
不動産の所有者と債務者が異なり、所有者が存命であれば、債務者のみを変更する必要があります。
所有者と債務者が同じ場合と同様に指定債務者登記が必要ですが、手続きの段取りが異なる点に注意が必要です。
債務を引き継ぐ指定債務者の決定は、債務の相続人と根抵当権者がおこないます。
根抵当権者とは、根抵当権に基づき融資をおこない、不動産を差し押さえる権利を持つ金融機関などのことです。
一方、指定債務者登記を実施して情報を更新する手続きは、不動産の所有者と根抵当権者がおこないます。
根抵当権をそのままに不動産を相続する流れ
根抵当権を外さずそのまま不動産を相続するときは、まず債権者である金融機関に連絡し、手続きに必要な書類を受け取ります。
もし、複数の相続人がいる場合は、遺産分割協議によって誰が不動産と根抵当権を相続するかを決めます。
事業の承継が含まれている場合は、新しく会社の代表となる方が相続するのがスムーズです。
相続する方が決まったら、相続登記、根抵当権の債務者変更登記、指定債務者の合意の登記をおこないます。
ただ、不動産の所有者が被相続人でなく、相続の発生に伴い所有権を別の方から相続人に移す場合は、所有権移転登記が必要です。
指定債務者登記では、不動産の権利証や印鑑証明書、会社所有の不動産であれば資格証明書または会社謄本、変更契約書または登記原因証明情報などの書類が求められます。
また、相続開始前の債務は相続人全員が分担して負いますが、指定債務者以外の方が免責的に債務を負う場合は、債権の範囲の変更登記をおこないましょう。
相続した不動産の根抵当権を抹消する方法

故人の代で事業を畳んでそれ以上根抵当権を設定しておく必要がないなど、不動産の根抵当権を抹消したい相続人の方もいます。
根抵当権を抹消するための流れは、債務がどれだけ残っているかによって異なるため注意が必要です。
債務が残っているパターン
根抵当権を抹消するためには、それまでに借りた債務を完済する必要があります。
該当の不動産を売却して債務を完済し、そのまま根抵当権を抹消する手続きをおこなうのが一般的です。
または、元本を確定させて根抵当権を抵当権に変更したうえで相続する方法もあります。
不動産を売却するときは、売却価格が根抵当権による債務を上回っている必要がある点に注意しましょう。
債務の金額によっては相続放棄も検討する
不動産の売却代金で根抵当権の債務を完済できれば、スムーズに根抵当権を抹消できますが、売却価格が債務の残高を下回ることもあります。
その場合、不動産を売却しても債務を完済できず、自己資金による返済が必要となります。
そのため、根抵当権がある不動産を含む相続財産の相続放棄を検討することも一つの方法です。
ただし、相続放棄を選択すると不動産以外の財産も相続できなくなるため、基本的には相続財産の総額がマイナスになる場合に選択することが望ましいです。
また、相続放棄は相続開始から3か月以内におこなう必要があるため、早めに検討することが求められます。
債務が残っていないパターン
根抵当権に基づく債務が残っていなければ、そのまま根抵当権を抹消できます。
ただし、根抵当権を抹消するには、設定している金融機関の同意が必要です。
金融機関によっては、抵当権以上に根抵当権の抹消に慎重な場合もあります。
同意が得られなければ、手続きに必要な書類を作成してもらえないため、相続を機に根抵当権の抹消を相談することが重要です。
根抵当権を抹消した不動産は通常の不動産として売却でき、売却代金を相続人同士で分配して相続することも可能です。
事業を承継しない場合、根抵当権は不動産売却の妨げとなりメリットが少ないため、早めに抹消することが望ましいでしょう。
なお、根抵当権を抹消する登記手続きには1万円から3万円の費用がかかります。
まとめ
根抵当権とは、不動産を担保に極度額まで何度も借り入れができる権利です。
これをそのままにして不動産を相続するときは、指定債務者を更新する登記が求められます。
もし、抹消したいのであれば、発生している債務を完済してから根抵当権抹消登記を実施しましょう。
他社で断られた物件を売却するなら「スグウル」へ
売主様の事情では、現地に行くのも嫌だ、、といったお客様も多数いらっしゃいます。
様々な悩みを抱えている売主様によりそって対応いたします!
お客様の方で、荷物を片づけたり、解体をしたりお手間を取らせることはございません。
もし他社様で雨漏り、訳あり物件の買取で費用を請求された場合や買取金額に納得いかない場合は、当社にご相談ください。
請求費用の減額や買取金額UPをできる限り頑張ります!
あきらめて、お金を払う前に一度スグウルにご相談ください









 人気のタグから記事を探す
人気のタグから記事を探す